弱アルカリ性がメダカを長生きさせる

メダカは弱アルカリ性に傾いた水で飼育を行った方が良いと言われ、
アルカリ性によって特徴が綺麗に現れる品種もいる。
水質悪化する際には酸性に傾いていると思われます。
アルカリ性を目指すことでメダカを長生きさせましょう。
飼育経験を元に飼育水をアルカリ性に近づける方法を紹介します。
アルカリ性になる素材

- 珊瑚
- サンゴ砂
- レンガ
- 瓦
- 溶岩
- 富士砂
- くん炭
- 古代米の藁
- グリーンウォーター
飼育水をアルカリ性に近づけるために使用していました。
過剰な投入は急激な環境変化を招き、phを上昇させるため
少しずつ加えていくことで、メダカの様子を伺いましょう。
購入したばかりの微塵が付着していることが大半なので、
使用する前に洗い落としましょう。
くん炭は水に浮かび上がりやすく、洗ってもボロボロになる上に
水を黒く汚すため使用方法に注意する必要があります。
[chat face=”6807C305-7802-43EA-A69B-C50DA0ADF3A0.jpg” name=”カメ太” align=”left”border=”gray” bg=”none” style=””]グリーンウォーターは光合成をおこなうことによってアルカリ性になるようです。[/chat]
弱アルカリ+水質浄化作用
- 牡蠣殻
- 卵の殻 (電子レンジで過熱済み)
- 竹炭
多少効果はあるようですが、アルカリ性を高めるというよりも、
水質悪化を避けるために利用していました。
酸性の際にカルシウムが溶けて中性から弱アルカリ性に傾けると言われていますが、
溶けて薄くなったり、無くなるということはありませんでした。
購入したばかりの微塵が付着していることが大半なので、
使用する前に洗い落としましょう。
竹炭は浮きやすいので使用する際には気を付けましょう。
グリーンモスを巻きつけたり、おはじき等の重りによって、
強引に沈めることが出来ます。
酸性に近づけようとするもの

- ミナミヌマエビ等の混浴生物の糞
- 雨水
- 有機物質の腐敗
混入しないための対策や定期的に確認を行うことによって、
アルカリ性に傾けるための努力が無駄にならないようにしましょう。
紅龍とは

アルカリ性に傾けるなど特別な環境で飼育することによって、
体色が紅色になると言われているメダカです。
雨が殆どはいらない状態で屋外飼育していました。
2年近く飼育していた経験を元に紅龍メダカを紹介します。
紅龍の一生

子メダカに完全な紅色を引き継がせることが出来ませんでした。
その上での紹介になりますので、飼育方法等が間違っている可能性が
ありますのでご注意ください。
黒が混じった卵
針子になるまで透明色の個体や体色に黒が混じる個体など様々です。
数十個の卵のうちアルビノになる個体が現れます。
[chat face=”6807C305-7802-43EA-A69B-C50DA0ADF3A0.jpg” name=”カメ太” align=”left”border=”gray” bg=”none” style=””]親メダカの影響を色濃く受け継がれやすい印象です。[/chat]
アルカリ性の水槽で飼育することで、針子の段階から体内が赤色になりました。
赤茶の体色の若魚
「紅白色の個体」や「赤茶と黒い鱗のブラックリムが混じる個体」「アルビノ」
など様々現れました。
腹ビレの無いオスが現れることが多くありました。
藻に付着糸を絡ませる個体がいて、毎日卵が産卵床に無いことがよくありました。
1年目
紅龍メダカの卵を入手することで飼い始めました。
様々な体色の個体が現れるため、「赤茶色と黒い鱗のブラックリム」のみを選び出して、
それだけが現れやすくするように努めました。
[chat face=”6807C305-7802-43EA-A69B-C50DA0ADF3A0.jpg” name=”カメ太” align=”left”border=”gray” bg=”none” style=””]ミナミヌマエビと混泳させていました。[/chat]
2年目
冬眠前に混泳を止め、掃除や水替えを行うことで紅龍のみで飼育していました。
[chat face=”6807C305-7802-43EA-A69B-C50DA0ADF3A0.jpg” name=”カメ太” align=”left”border=”gray” bg=”none” style=””]越冬を経験させることにより、赤色が濃くなるように思います。[/chat]
赤に近づいた個体がいましたが、確率が全く上がらないので、
現在は選別作業をしておりません。
強アルカリ性はダメ
アルカリ性がメダカによって好む場所であっても、底床でバクテリアを増やしても
強アルカリ性になった途端にアンモニアが分解出来ない環境となり、
メダカが弱っていきます。
最近まで、4L水槽かつ加温状態でアルカリ性に近づく底床を利用していました
1週間の水換えでは追いつかないほど、アンモニアが増加してしまい、
メダカが弱ってしまい、底床を見直すことにしました。
まとめ

- 飼育水を急激にアルカリ性に変えてしまうとメダカが死滅してしまう
- 有機物質の腐敗は酸性に傾け、急激な環境変化を起こす
- 強アルカリ性になった途端にアンモニアを分解出来ない環境になりメダカが弱ります

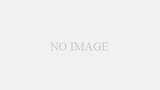

コメント